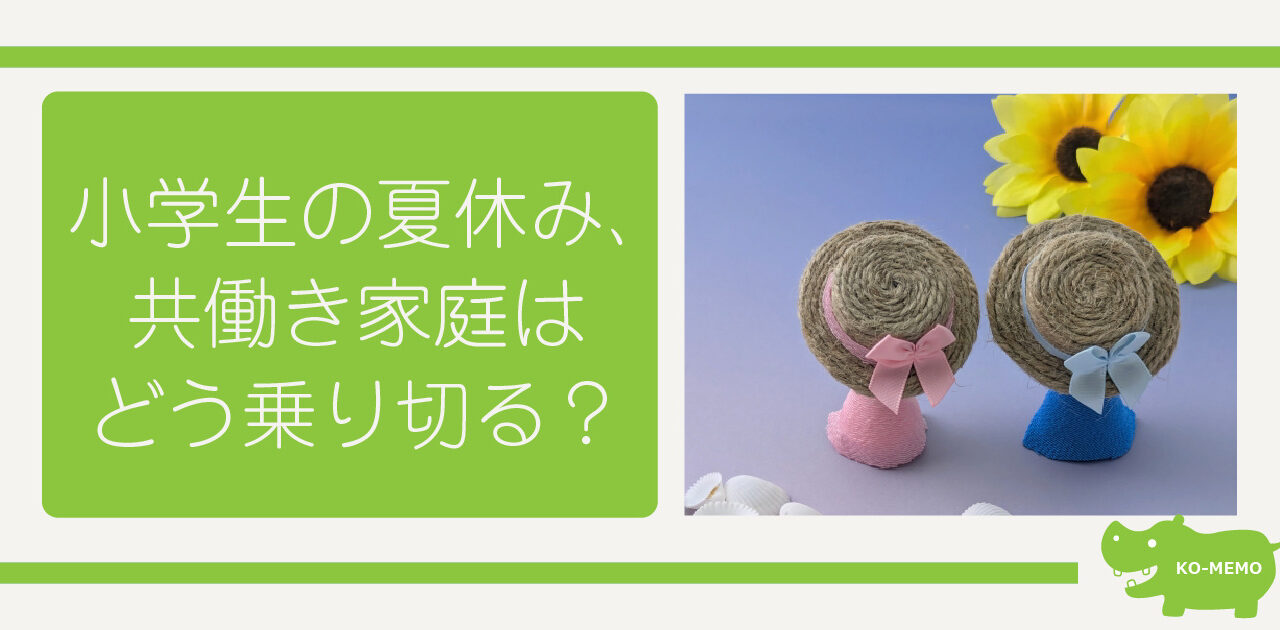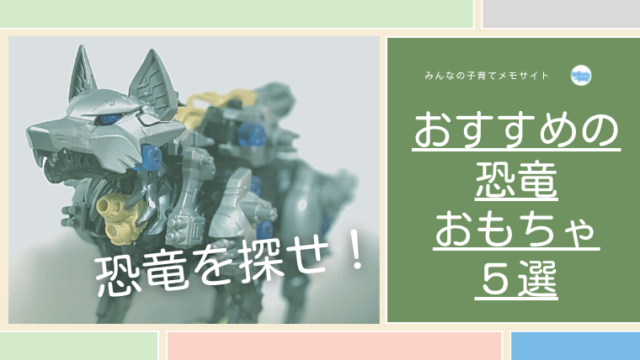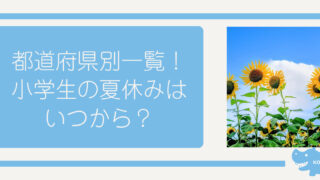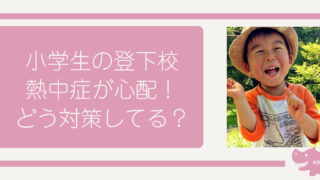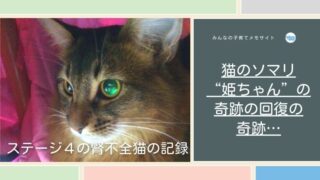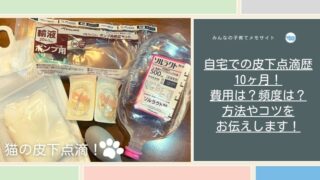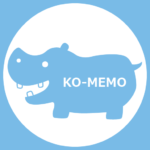Contents
小学生の夏休み、共働き家庭はどう乗り切る?
夏休みが近づくと、共働き家庭の親にとって頭を悩ませるのが「子どもの預け先問題」。
保育園時代とは違い、小学生になると急に”預けにくさ”を感じることもありますよね。
今回は、小学生男子を育てる筆者が、実際の経験をもとに、夏休み中の預け先やその選択肢、我が家の対策などを紹介します。
小1の壁、小4の壁ってなに?

小1の壁とは?
小学校に入学した途端に直面するのが”小1の壁”。
- 学校の登校時間が遅い/下校時間が早い
- 夏休みなど長期休暇の預け先に困る
- 学童保育の定員問題 など、保育園時代にはなかった壁が待ち受けています。
筆者の住む市は、希望する生徒はほぼ100%学童保育に入ることができています。
(希望の場所に入れないことはありますが・・・)
一方、隣の市では、人気の学区では学童入学が至難の業で、学区内になる友人の会社では例年小1の壁で退職する方がいるそうです。
解消されてきたとはいえ、まだまだこの壁に当たる人は多いはず・・・。
小4の壁とは?
小4になると、学童を辞める子が増え始めます。
- 子どもの自立心が出てくる
- 学童の雰囲気が合わなくなる
- 勉強や習い事との両立が難しくなる
学童自体が3年生という自治体も多く、さらに子供が「学童いや!」という場合も多いようです。
これも筆者の周りですが、女の子は人間関係の複雑さから学童をやめる子が多いです。
実際息子の学童は、男の子は仲良しなので4年生でも15人ほどが通っていますが、女の子はどんどん辞めていき、今は4人しかいません・・・。
我が家の場合:学童大好き男子の夏休み
筆者の子どもは、小1から迷いなく学童に通わせました。
しかも、保育園時代からの仲良しメンバーがそのまま学童に在籍しているという奇跡のおかげで、息子は学童が大好きに。
むしろ「夏休みはずっと学童にいたい」と言われるほどで、4年生の今も変わらず。お友達が我が家に遊びに来ることもあり、学童が単なる”預け先”を超えて、”居場所”になっていると感じています。
今年も学童でお世話になります、ドラゴンドリル。
息子たちはこのドリルを自習時間に行い、シールを張って完成したドラゴンで謎の遊びをしています。
もう、何冊買ったかわかりませんが、この夏は都道府県と3年生の総復習、から始める予定です!
学童保育って、どうやって探すの?

自治体の公設学童
まず最初に確認したいのが、自治体が運営する公設学童。
- 申請時期が早い(秋~冬頃)
- 所得制限がある地域も
- 小6まで利用可能な自治体もある
筆者の地域は、小6まで学童利用が可能。地方ならではの余裕もあるようで、受け皿が比較的広い印象です。
夏休み等の長期休暇のみ利用も可ですが、新小1の時以外は小学校からの案内もないので、アンテナを張っていないと申請漏れの可能性もあります。
民間学童
最近では、民間学童の選択肢も増えています。
- 学習サポートや習い事連携がある
- 延長保育が可能
- 費用はやや高め
送迎バス付きなど、共働き家庭にはありがたいサービスも多くあります。
都会では、学習塾が運営するもの、英会話スクールが運営するもの、などがあります。
筆者の住む都会と田舎ぐらいの街では、上記サービスが受けられるのは市の中心部のみ。
駅から離れると、上記スクールの送迎範囲から出てしまう感じです。
学童以外の選択肢は?

留守番(低学年~高学年)
学年が上がると、家でお留守番という選択肢も。
- 低学年:短時間からスタート
- 高学年:ルールをしっかり決めれば可能
女の子は人間関係の難しさから学童を辞める子も多く、お留守番にシフトする家庭も。
兄弟がいる場合は、お留守番の選択肢が急浮上するようです。
ただ、子どもだけで家にいる場合、万が一の場合の心配とゲームやyoutubeばかりにならないかが心配ですよね・・・。
子供だけでお留守番の場合、見守りカメラなど設置しておきたいところ。
できれば双方向でコミュニケーションが取れるとなお◎
習い事・サマースクール
- スイミングやプログラミング教室
- 英語キャンプ、地域のワークショップなど
学童+習い事でスケジュールを埋めるスタイルも人気です。
学童だけだと、閉鎖的な空間で長期間を過ごすことになるので、おすすめです。
祖父母や親戚の助けを借りる
夏休み中、1週間だけ祖父母の家へ…という家庭も。
親子ともにリフレッシュできる貴重な機会になります。
友人のところは、子どもだけで新幹線に乗り、2週間ほど祖父母の家に行くそうです。
(新幹線乗り場まで見送り、姉妹だけで新幹線。祖父母が駅のホームまでお迎え、で行くそう!)
地域によって差がある?
筆者の住む地域では、少子化の影響か学童の受け入れに余裕がある印象。特に地方ではその傾向が強いようです。
一方、都市部では今でも学童の競争率が高く、民間学童を併用する家庭も多いと聞きます。住んでいる場所によって、選択肢や戦略も大きく変わってくるのが現実です。
夏休み、親子で乗り切るための工夫

スケジュールの見える化
- カレンダーに予定を書き込む
- 子どもと一緒に予定を確認する
子どもに「選ばせる」
学童に行くか、どの習い事に通うかを子ども自身に決めさせることで、自主性を育てつつスムーズなスケジュール管理ができます。
無理しない。割り切る。
全日埋めなくても大丈夫。たまのお昼寝やゴロゴロ時間も必要な夏休み。親も無理せず「まあいいか」の精神で!
まとめ:正解はないけれど、選択肢はある
小学生の夏休み、預け先問題に明確な正解はありません。家庭の状況や子どもの性格、地域性によって、選ぶべき道は変わります。
我が家のように「学童大好き男子」なら、親としては安心してお願いできる。でも、すべての子に学童が合うとは限りません。
大切なのは「家庭にとってのベスト」を探すこと。少しでもこの記事が、そんな選択の参考になれば嬉しいです。